畑の作物や花壇の花にアブラムシがついてしまった時に、農薬を使わずに防除したい場合には「天敵を使った生物学的防除」という方法があります。
アブラムシはウイルス病を媒介する厄介な害虫ですが、アブラムシ自体は移動能力や攻防能力をほとんど持たないとても弱い虫です。
そのため、自らが排泄する甘露という甘い分泌物を餌に、アリをボディーガードとして従えて天敵を追っ払ってもらう「共生」を行っています。
甘くて柔らかいアブラムシには多くの天敵がおり、それらの天敵を使ってアブラムシを防除してしまうことが出来れば、農薬も必要ないし経費も節約できるでしょう。
今回は、アブラムシの天敵の種類とその特徴をご紹介したいと思います。
天敵を用いる生物学的防除方法のメリットについて

農作物や花を育てていると、様々な病害虫がいることに気が付きます。
防除の方法として農薬や殺虫剤が第一選択になることが多いのですが、アブラムシの場合はできるだけ農薬を使わない方法が好まれます。
その理由としては、
- 同一系統の薬剤を継続して散布することで、薬剤抵抗性を持つ個体が増える
- 天敵が多く、生物学的防除方法が有効になりやすい
- アブラムシの種類によっては様々な種類の作物に付くために、農薬での防除が手間である
などが挙げられます。
特に①においては、これまでに作られてきた代表的な殺虫剤たちに対して抵抗性を持つアブラムシが増えてきているために、世界的にも問題になっているのです。
特に「ワタアブラムシ」と「モモアカアブラムシ」の2種は、有機リン剤、カーバメート剤、合成ピレスロイド剤などの薬剤が効かなくなってきている代表的なアブラムシです。
これらのような抵抗性を持つアブラムシが今後出ないとは限らないので、極力農薬を使わない天敵を使った防除方法などを進めていくというのはとても大切なのです。
※アブラムシについてのより詳しい生態については「アブラムシはどんな害虫?農家の敵アブラムシの生態まとめ」の記事をご覧ください。
アブラムシの天敵の種類と特徴について
1.テントウムシ類

アブラムシの天敵として真っ先に名前が挙がるのが「テントウムシ」でしょう。
成虫も幼虫もアブラムシが大好物で、気温が温かければ一年中アブラムシを捕食します。
テントウムシは、大きく分けると「肉食性」「菌食性」「草食性」の3種類おり、アブラムシを捕食するのは「肉食性」のテントウムシです。
「肉食性」「菌食性(うどんこ病菌などを食べる)」は益虫であるに対して、「草食性」のテントウムシはナスの葉なども食べてしまうので、農家にとっては害虫に分類されます。
では、アブラムシを捕食してくれる肉食のテントウムシにはどのような種類がいるのでしょう。
【アブラムシを食べる肉食のテントウムシの種類】
ナナホシテントウ/ナミテントウ/ダンダラテントウ/ヒメカメノコテントウ/ジュウサンホシテントウ/ウンモンテントウ/オオテントウ など
ヒメカメノコテントウ

上の画像は、ヒメカメノコテントウ。
小型のテントウムシですが、食欲が旺盛で1日に50匹以上のアブラムシを捕食してくれます。生涯4000匹ものアブラムシを食べるといわれているそうです。また、アブラムシ以外にも、コナジラミなどの害虫を食べてくれるとても頼りになるヤツなんです。
このヒメカメノコテントウは、アブラムシ対策として商品化もされています(商品名:カメノコS)。
ナミテントウ

ナミテントウは、赤一色のナナホシテントウとは違い、黒やオレンジの種類がいます。
成虫、幼虫ともアブラムシを捕食し、食欲旺盛で1日に50~100匹も食べるので、アブラムシにとっては一番の天敵です。
このナミテントウの捕食力を生かすべく研究がすすめられ、近年では「飛ばないナミテントウ」として施設野菜用の天然製剤「テントップ(商品名)」が販売されています。
飛ぶ能力の低いナミテントウを選抜して交配を繰り返すことで作られた「飛ばないナミテントウ」は、飛んで逃げることなくアブラムシを捕食し続けてくれます。
価格は少々高めですが、農薬を使わずに、安全かつ継続的にアブラムシを捕食してくれるので、飛ばないナミテントウの利用はかなり効果が高いのでおすすめです。
アブラムシの発生を確認したらすぐに購入する必要があるぞい!
2.寄生バチ類

※画像はチャバラアブラコバチ
アブラバチ系の寄生バチは、アブラムシの体に卵を産み付けます。
アブラムシの体内で育った幼虫は、アブラムシの養分を吸い取って成長し、最後には宿主であるアブラムシは死亡します。
寄生バチの種類によっては、生涯300~500個の卵をアブラムシに産み付けるので、アブラムシの防除としてはとても有効性が高いです。
【アブラムシに卵を産み付ける寄生バチの種類】
コレマンアブラバチ/ギフアブラバチ/チャバラアブラコバチ/ナケルクロアブラバチ など
コレマンアブラバチが資材化された「コレトップ」のほか、ギフアブラバチの資材「ギフパール」、チャバラアブラコバチの「チャバラ」など、様々な寄生バチ資材が販売されています。
3.ヒラタアブ

テントウムシと並んで、アブラムシの最重要天敵とされるのがこの「ヒラタアブ」です。
その見た目から「ハチ」と間違えられやすいのですが、ハエの仲間です。
成虫は花粉や花の蜜しか食べないのですが、幼虫は500匹以上のアブラムシを食べるといわれています。
幼虫は捕まえたアブラムシの体液を吸って外側の殻だけにしてしまいます。

ヒラタアブの幼虫は、半透明な蛆虫のようで見た目は害虫のようですが、沢山アブラムシを食べてくれる益虫ですので、駆除してしまわないようにしましょう。
4.クサカゲロウ

クサカゲロウもアブラムシの天敵として知られています。
成虫はアブラムシが分泌する甘露や花粉を食べますが、アブラムシ自体は捕食しません。クサカゲロウの幼虫は、成虫になるまでに300~600匹のアブラムシを食べるといわれています。

※クサカゲロウの幼虫
5.ショクガタマバエ

※画像はタマバエの一種
タマバエの仲間は、世界中に4600種類以上が見つかっており、ハエというよりも蚊に近い昆虫です。
その中でも「ショクガタマバエ」の幼虫は、アブラムシを沢山捕食するので生物学的防除に利用されます。

※ショクガタマバエの幼虫
口吻をアブラムシに刺して、「毒液を注入して痺れさせてから体液を吸う」というコロンとした見た目からは想像しにくい食べ方をします。
この幼虫1匹で約100匹のアブラムシを食べてくれるといわれています。
6.ヒメハナカメムシ

(※修正 2018/4/7 :誤った画像を掲載していたため修正いたしました)
ヒメハナカメムシ類は、比較的暖かい地域に生息しており、シロツメクサなどに集まるアザミウマなどの害虫を食べにやってきます。
アザミウマ以外にも、アブラムシはもちろん、ダニなどの小さな虫を捕食します。
ヒメハナカメムシも、ナミテントウなどと同様に生物農薬として販売されています。
天敵を利用してアブラムシを駆除する方法

ここまでに紹介した数々のアブラムシの天敵ですが、ただ畑であぐらをかいて待っていればどこからかアブラムシを食べにきてくれるわけではありません。
前述した「テントップ」や「リクトップ」など商品化された生物農薬を購入して増やす方法が最も簡単で効果的ですが、アブラムシを発見してから、ただ天敵を放すのでは効果が不安定になりがちです。
購入した天敵を利用する際に一番難しいのが「作物に放すタイミング」です。
アブラムシが発生してすぐに大量の天敵を放すと、餌となるアブラムシが少なすぎて天敵が減ってしまいますし、逆に天敵を放すタイミングが遅すぎると捕食が追い付かずに作物がやられてしまうでしょう。
近年では、天敵を貯蓄して待ち構える「バンカー法」を行って、常にハウス内に天敵がいる状態にする方法が注目されています。
露地栽培をしている場合でも、ソルゴー(ソルガム)を使った障壁を作り、土着天敵を呼び込む方法も効果があります。
バンカー法とソルゴーの利用については、「ソルゴーの種類とバンカー法のアブラムシ防除効果について」で詳しく説明をしていますので併せてご覧ください。
天敵を利用した生物農薬の効果を最大限活用するためには、「天敵がいかに長期間滞在してアブラムシを捕食できるような環境を用意できるかどうか」という点にかかってきます。
天敵が安定供給できるようなバンカー法を圃場に用意することが出来れば、農薬散布の回数も減り、農薬代と散布にかかる作業時間を大幅に減少させることが出来ます。
さらに、天敵を利用した生物農薬では薬剤抵抗性のあるアブラムシを増殖する恐れもないので、長期的に見てもメリットは大きいでしょう。
まとめ
【天敵を利用した生物農薬のメリット】
- 薬剤抵抗性を持ったアブラムシを増やす危険性が無い
- 農薬散布が減り、安全性の向上・経費の削減・散布にかかる作業時間の削減ができる
- バンカー法を使えば安定した天敵の供給ができ、アブラムシを未然に防ぐことが出来る
【天敵を用いたアブラムシ防除法の注意点・デメリット】
- 天敵を作物に放すタイミングが難しい
- バンカー法でないと、安定した天敵の供給が難しい
- 販売されている生物農薬(天敵)は、いずれも高価である
- ソルゴーなどのバンカーに使う植物を育てるタイミングをアブラムシの発生時期に合わせる必要があり、タイミングが難しい
上記のように、天敵を用いたアブラムシの防除法は、実施するタイミングや天敵がアブラムシを上手く駆除してくれているかどうかの効果判定が難しいのが注意点です。
生き物任せで防除するので、仕組みを構築するまでにある程度の時間がかかります。
辛抱できずに農薬をまいてしまうと、餌を食べにやってくるはずの天敵がいなくなってしまったり、天敵ごと駆除してしまうなんてことが起きてしまう。
天敵を用いた防除をする場合は、すぐに薬をまかない忍耐力と防除のタイミングを見極める観察力が求められるでしょう。
しかし、一度しっかりとした生物学的防除の環境が確立できれば、そこから得られるメリットはとても大きなものになります。
また、「農薬を使わずにアブラムシを防除する6つの方法」の記事で、天敵による防除以外の無農薬アブラムシ防除法をご紹介していますので、こちらも是非ご覧ください。
天敵を用いた防除方法についてのより専門的な知識をお求めの場合は、下記の「天敵活用大辞典」が参考になるでしょう。
<アブラムシについての関連記事はこちら>


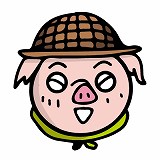





ヒメハナカメムシとして連載されている画像の虫は、トコジラミです。
管理人です
ご指摘いただきありがとうございました。
手違いで誤った画像を挿入していました。
修正して更新いたしました。